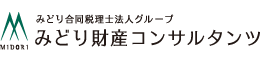2025年09月18日
Slackを使用し始めました!

私たちの会社では、業務の効率化とコミュニケーションの改善を目的に、新しくSlackを導入しました。ITツールに詳しい人からは「メールよりスピーディーに意思疎通できる」「社内の情報共有が活性化する」といった評価をよく耳にしていました。しかし、実際に導入してみると、メリットを享受する以前に、慣れるまでの大きな壁が存在することを痛感しており、日々苦闘しています。
まず直面したのは「情報の流れの速さ」による混乱です。チャンネルごとにやり取りが進むため、数時間席を外しただけで大量のメッセージが積み上がり、大事な情報を見落としかねません。従来のメールであれば件名やスレッドである程度整理されていましたが、Slackではスピード感が優先される分、利用者が主体的に整理・検索する力が求められます。この点で、むしろ業務の効率が下がったと感じる場面も少なくありませんでした。
次に難しさを感じたのは「使い方のルール作り」です。スタンプひとつにしても、「確認しました」の意味で使うのか、単なる気軽なリアクションなのか、メンバー間で解釈がばらつきます。スレッドを活用すべき場面と、オープンなチャンネルで議論すべき場面の切り分けも曖昧で、最初のうちは混乱が続きました。結局のところ、ツールの機能自体よりも、それをどう使いこなすかという“運用ルール”の整備が効率化の鍵になるのだと実感しています。
しかし、導入から時間が経つにつれ、Slackならではの強みも見えてきました。検索機能を駆使すれば、過去の議論やファイルにすぐアクセスできます。チャンネルを横断した情報共有により、部署を超えた連携が以前より円滑になりました。また、メールではどうしても「正式な連絡」に偏りがちでしたが、Slackではちょっとした相談や雑談も気軽に交わせるため、組織全体の心理的な距離が縮まるという副次的な効果も感じています。
導入初期は「逆に非効率ではないか」と疑問を持つ瞬間もありましたが、それはあくまで過渡期の現象にすぎないと感じております。大切なのは、ツールに振り回されるのではなく、自社に合った使い方を模索し続けることだと思います。
Slack導入はゴールではなく、効率化の第一歩。今後は運用ルールを整備し、社員一人ひとりが「情報の受け取り方」と「発信の仕方」を意識することで、ようやく本来のメリットを享受できるのだと思います。
Slackは、単なるチャットツールではなく「組織の働き方を変えるインフラ」です。効率化の効果を最大化するためには、仕組みづくりと人の意識改革が不可欠であり、その取り組み自体が会社の成長に直結していくと考えてるので、負けないように頑張っていきます
今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。